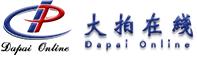大拍在线 资讯公告
トビイカ有望漁場フィリピン東、水研機構が調査報告会
2017-03-16 08:47:14
2017年03月16日 日刊水産経済新聞
新たな加工原料として注目が高いトビイカに関して、北赤道海流海域より北の海域が好適な漁場であることが分かった。水産研究・教育機構開発調査センターが1~2月にイカ釣り船による漁業の可能性を初めて調査したその結果を、14日に八戸市内で主催したシンポジウム(全国いか釣り漁業協会、全国いか加工業協同組合後援)で報告した。

フィリピン東方沖調査で漁獲されたトビイカ
1月19~2月12日、フィリピン東方沖の公海で、中型イカ釣り船1隻と大型イカ釣り船1隻を使い、北赤道海流海域(北緯11度から17度)、同海域より北(北緯17度より北)、同海域より南(北緯11度より南)の3海域で商業的な漁獲ができるか調査した。その結果、北赤道海流海域より北の海域で、一操業当たり平均266尾、漁獲重量平均58キロ、外套(とう)長平均15・4センチのトビイカを漁獲。ほかの2海域はシケで操業できない日が多いことから、「北赤道海流海域より北の海域でなければ、漁業として成立しないことが分かった」(加藤慶樹調査員)。
北赤道海流海域より北の海域に絞り、自由操業で調査すると、「最後の2日間で一日1トン超を漁獲。商業ベースの兆しがみえ、希望がもてる結果が出た」(同)という。
アカイカ針よりマイカ針の漁獲が多く、小型の針が向いていることが分かった。減灯(真っ暗な状態でイカを浮き揚がらせる方法)を行うと、それまでを超える漁獲があり、かなり効果的だった。
新たな加工原料として注目が高いトビイカに関して、北赤道海流海域より北の海域が好適な漁場であることが分かった。水産研究・教育機構開発調査センターが1~2月にイカ釣り船による漁業の可能性を初めて調査したその結果を、14日に八戸市内で主催したシンポジウム(全国いか釣り漁業協会、全国いか加工業協同組合後援)で報告した。

フィリピン東方沖調査で漁獲されたトビイカ
1月19~2月12日、フィリピン東方沖の公海で、中型イカ釣り船1隻と大型イカ釣り船1隻を使い、北赤道海流海域(北緯11度から17度)、同海域より北(北緯17度より北)、同海域より南(北緯11度より南)の3海域で商業的な漁獲ができるか調査した。その結果、北赤道海流海域より北の海域で、一操業当たり平均266尾、漁獲重量平均58キロ、外套(とう)長平均15・4センチのトビイカを漁獲。ほかの2海域はシケで操業できない日が多いことから、「北赤道海流海域より北の海域でなければ、漁業として成立しないことが分かった」(加藤慶樹調査員)。
北赤道海流海域より北の海域に絞り、自由操業で調査すると、「最後の2日間で一日1トン超を漁獲。商業ベースの兆しがみえ、希望がもてる結果が出た」(同)という。
アカイカ針よりマイカ針の漁獲が多く、小型の針が向いていることが分かった。減灯(真っ暗な状態でイカを浮き揚がらせる方法)を行うと、それまでを超える漁獲があり、かなり効果的だった。
大拍在线服务电话(+86)15940823456
Copyright©2016版权所有 大拍在线 版权所有 辽B2-20170243
辽公网安备 21020202000043号